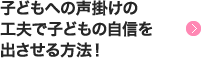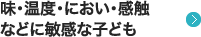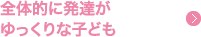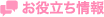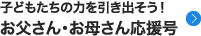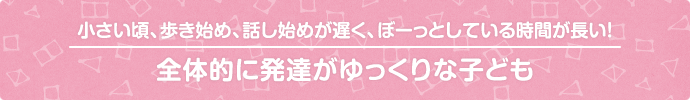監修/久保田千鳥:ちどりこどもクリニック院長、小児科医

例えば・・・小さい頃は歩き始めや話し始めが遅く、どちらかと言うとボーっとした子でした。
- ●お友達がふざけると、一緒になってふざけてしまう。
- ●先生やお家の人の話を聞いているように見えても、実際に指示通りには動けない。
- ●周囲の動きを見ながら、いつも一番最後に、みんなの後をついて動く。
- ●遊びの幅が狭く、新しい遊びに誘っても、あまり興味を示さない。
- ●全体的に動きがゆっくりで、活動的ではない。
- ●口数が少なく、言葉で上手に話せない。
- ●指しゃぶり、ツメかみ、体のどこかを触る。
運動・言葉・理解力など、全体的に年齢より発達が幼く、受動的で自ら積極的に動くことが苦手です。
複雑な指示や難しいルールゲームなどは、同齢の他の子のように理解することが難しいことも。
人が好きで、人に言われたことには従うので、周囲を困らせることはあまりありませんが、分からなくても自分から訴えられないため、集団の中に埋もれてしまいがちです。
- 注意しても、同じことを何度もくり返す!!
- 注意の内容が理解できていなかったり、教えられてもすぐに忘れてしまうのかもしれません。短い言葉で、分かりやすく簡潔に、あるいはジェスチャーや絵を描いて「×」を伝えたり、すべきことを具体的に伝えていくことが大切です。指示は1回に1つ、にしてみましょう。そして1つずつでも、できたらハナマル♪褒めてあげましょう♪
- 制作課題の時、作り方を説明してもきちんと理解できないみたい・・・
- 言葉の理解力が十分育っていないかもしれないので、年齢よりも幼い子に伝えるように簡潔で分かりやすい表現が伝わりやすいです。お手本や見本を置いたり、目の前でやって見せるなど、目で見て分かるような配慮をしてみましょう。
- 給食の準備など、動きに時間がかかり、その都度指示をしないとできない!!
-
活動の流れを細かいステップに分けて、一つ一つ練習していくと良いですね。上の例と同様、一緒にやって見せたり、給食袋の実物を見せて、ロッカーに取りに行くことを伝えるなど、目で見て分かる工夫が有効です。繰り返し行い、時間をかけて流れを理解していくことが大事ですね。スモールステップで、少しずつ身につけさせてあげたいですね。